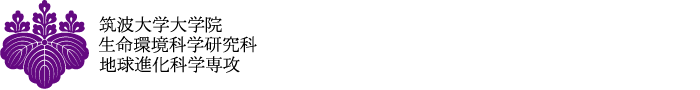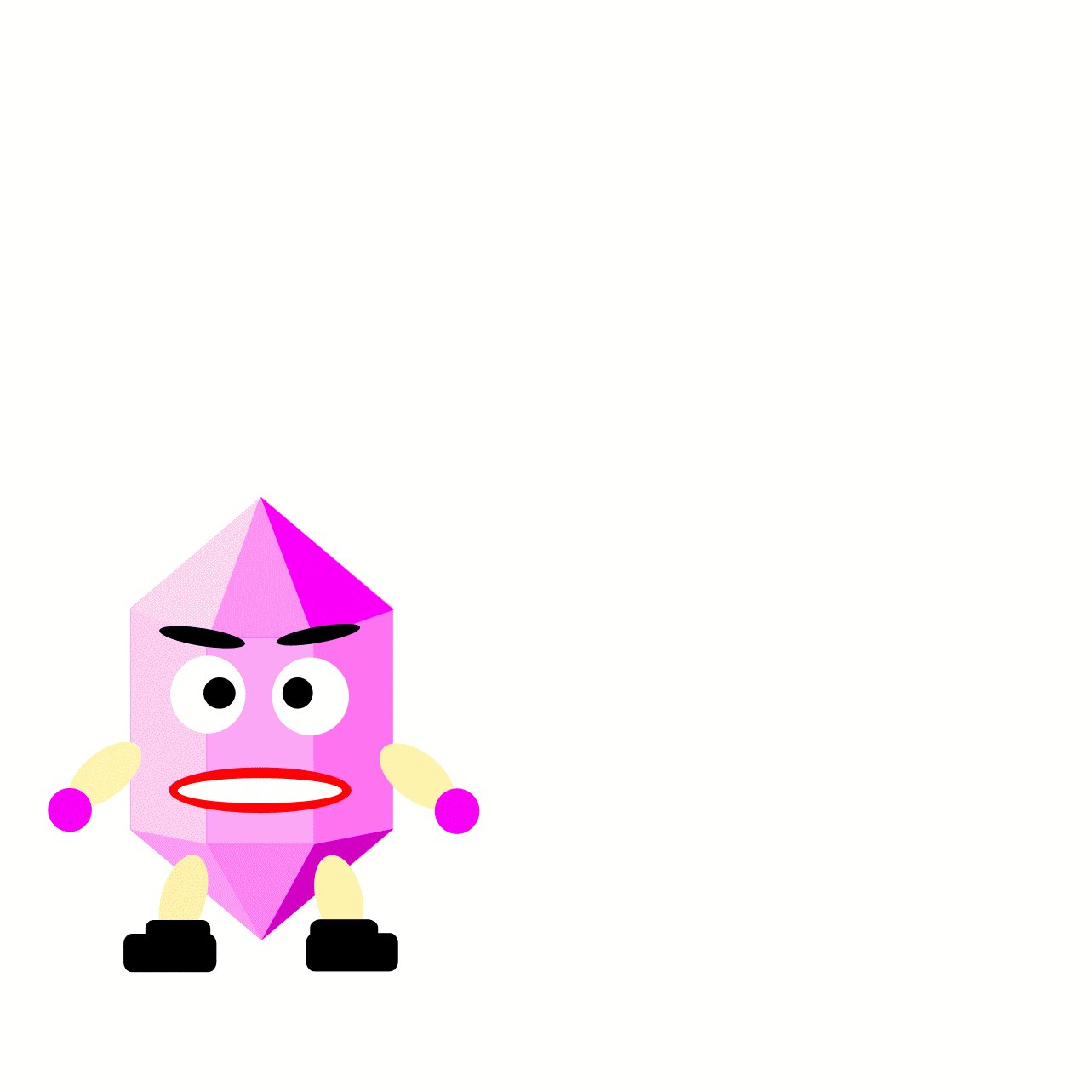■自然学類
・1年生
自然科学の教養課程として、数学、物理学、化学、地球科学の基礎を学習します。
・2年生
地球科学の全般の講義や実験を通して、地球の現象を知る上で必要となる基本的な理論や実験手法、野外調査方法について学びます。鉱物学に関係した講義には“地球物質科学”があります。
・3年生
地質学専攻と地理学専攻の2専攻に分かれます。鉱物学分野は地質学専攻の方に属します。地質学専攻では、3年次には、多くの専門科目と演習が開講されており、地球上の諸現象に関する幅広い専門的な知識を学びます。また、多くの野外実験や室内実験も開講されており、それらを通じて、これまでの講義で学んだ理論を自分の目で実際に検証して、学問的な理解を深めます。 また、研究の分野では世界共通言語である英語の読解力を習得するために、専門外書輪読も必修科目となっています。
◎鉱物学分野では、卒業研究で鉱物学分野に進みたい学生には、3年次に、“鉱物学”、“岩石・鉱物学演習”、“鉱物学実験”の科目を履修しておくことをお奨めしています。
・4年生
卒業研究を行うために研究室に所属します。研究室では、まずはじめに指導教官の先生と話し合って卒業研究のテーマを決定しますが、その場合には、学生の希望を出来るだけ尊重してテーマを設定するようにしています。研究テーマが決まると、研究室のスケジュールに沿って研究を進めます。卒業研究では、室内実験、野外調査、ゼミを通して、最先端の研究に触れることが出来ます。そして、研究を進めて明らかになった成果は、各研究室で主催される研究報告会で発表され、指導教官や大学院生と活発に議論を行いながら、完成度の高い卒業研究に仕上げて行きます。そして10月に、それまでの研究成果を、地質学専攻全体の中間発表会で発表し、最終的には、1月の卒業研究の最終発表会で、1年間の研究成果を発表します。そこで合格して、晴れて2月に研究成果を卒業論文として提出し、卒業を迎えることができます。
■大学院博士課程地球進化科学専攻 (五年一貫制)
鉱物学について深い理解と能力を養うと共に、その基礎となる幅広い視野と学識をもち、自立して研究活動を行える研究者の育成を行うことを目的としています。現在は、地球や惑星を構成する主要な鉱物の野外調査と記載、化学組成・結晶構造の精密決定、室内実験による合成を手法とし、鉱物の物性や生成機構、生成条件の解明を行っています。本専攻は五年一貫制ですが、必要条件を満たせば修士の学位も取得可能です。また、優れた研究業績(例えば国際誌に研究論文を3編掲載)を挙げたものについては、博士課程に3年以上在学していれば学位(博士号)を取得することもできます。
・地球進化科学特別演習(地質学セミナー)
筑波大学は、研究基盤総合センターなどの学内共同研究施設(→)が非常に充実しています。また、筑波研究学園都市という立地条件にも恵まれ、世界最先端の研究機関が大学周辺に数多く隣接しています。そのため、それらの実験施設を積極的に利用して研究活動を行うことができるという素晴らしい利点があります。しかし、第一線の研究者を目指す上では、鉱物学という分野だけにとらわれず、より広い視野で、自分の研究を客観的に評価する目も必要となります。したがって、他分野の教官や大学院生との活発な議論を行うために、研究成果を発表する場として、地質学セミナーが開催されています。大学院生は、年1回必ず、自分の研究成果を発表する必要があります。また、このセミナーでは、国内外から世界の第一線で活躍していらっしゃる講師の先生をお招きして、講演をしていただく回も設定されており、最先端の研究に触れられる場としても非常に有意義なものになっています。
・中間評価(修士論文)
鉱物学分野では、共通科目と専門科目を設け、前者においては地質学全般の幅広い知識と総合的な判断力を養う教育、後者においては専門書を教科書として、鉱物学の深い専門的知識を身に付けるための教育を行っています。また、鉱物学分野では、修士論文の提出を目的とするのではなく、その研究成果を、主に国外の学会誌や国際科学雑誌に投稿することを目標としています。本分野の多くの大学院生は、この目標を達成しています。また、博士課程前期では、博士課程後期の学位論文につながるような、科学的に意義のある研究テーマを、それまでに行った研究の中から見つけ出すことも重要です。つまり、修士論文は、研究者として自立できるか否かを見極めるための関門でもあり、研究者生活の出発点となります。
・学位論文審査及び最終試験(博士論文)
鉱物学分野では,各々の大学院生が広い視野と深い専門的知識を培い、創造性豊かな研究者としての成長を目指し、少人数制のゼミや個別的研究指導を中心とした多様な教育を行います。博士課程後期では、指導教官は、基本的に研究テーマについて助言はしますが、具体的な指示を与えることはあまりしません。大学院生には、あくまでも自らの力でテーマを発見し、研究を計画し、実験を行って、直面した難題は自らの力で突破するような研究の推進力が要求されます。そして、国内だけでなく、国外の学会にも自主的に参加して、国際的な研究者としての見識を広げ、さらに、世界的に注目度の高い国際誌に原著論文を数多く投稿し、鉱物学全体の進歩に寄与するような質の高い研究を行うことが必要となります。学位論文審査及び最終試験では、学位論文の内容だけでなく、それまでの研究活動、研究業績、さらには、研究者としての将来性、世界の最先端で活躍できるポテンシャルなどが審査されます。そして、それらが認められてはじめて合格となり、晴れて学位(博士号)を取得することが出来ます。