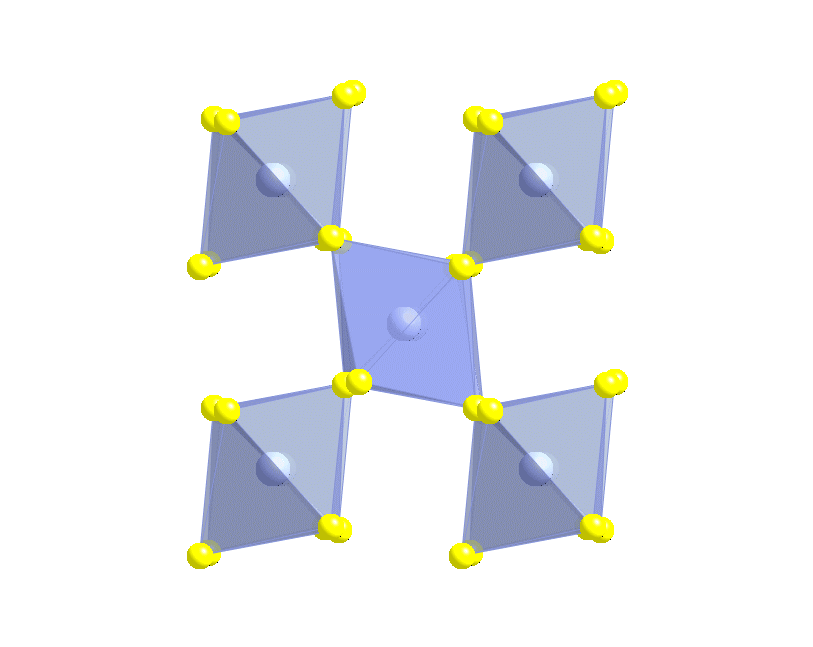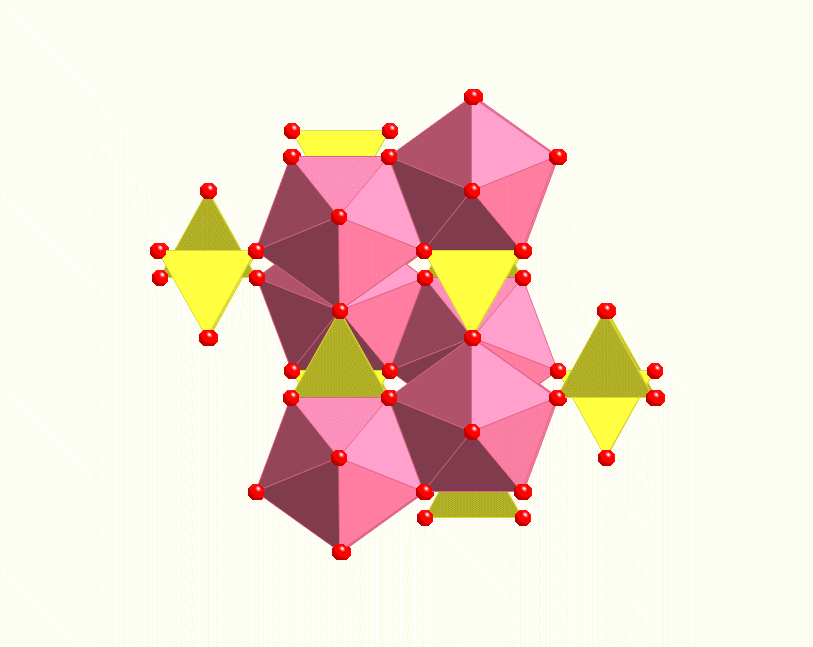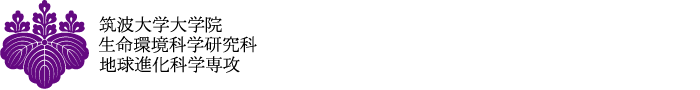![]()
地球科学という学問は、三十年前までは、ほとんどが地質学▪鉱物学と地球物理学という分野でなされてきたが、過去も現在も、地球物質科学の核心的役割を果たしてきたのが、「鉱物学」である。それだけに学問分野間のスペクトル性が強い地質学や物質科学に風通しのよい堅実な視力を向けて発達してきた「鉱物学」は、科学の総合力によって構築されているといっても過言ではない。単に鉱物だけの知識を堆積しただけでは、鉱物の本質、即ち鉱物学の根本原理に触れることは不可能である。「研究」とは「学問」を使い熟せて初めて可能になるものであり、それができないと、「趣味」に陥る。専門力は基礎力と総合力に支えられて、如何なく発揮される。従って、鉱物学には、基礎学力と総合力を持っている人間ほど、より高度な専門力を発揮でき、科学の醍醐味という琴線に触れることができる。また、鉱物学が社会に貢献する役割を持つことは、自然科学の一分野を構成する学問として当然であるが、他の学問に対する鉱物学的視力と社会組織の理解という確固たる総合認識を持たなければ、その責務を果たすことはできない。
鉱物学は鉱物を研究する学問であるが、他の自然科学には無いユニークな時空次元を保有する。数学、物理学、化学の自然科学は、時間·空間を超越した普遍の原理、原則を追及する学問として発達し、向上している。しかし、「生物学」及び「地質学と同舟する鉱物学」は、それに地域性と歴史性が加わり、46億年の「地球の進化」が育んだ単純かつ複雑な学問として成長した。鉱物には(1)戸籍(産地と生成年代)、(2)物性(組成と結晶構造)が必ず伏在する。地球の進化が出現させた大陸、島弧、海洋、海嶺、火山島、及び地球誕生以前の隕石や惑星などから産出する鉱物の様々な知識·情報には、普遍原則、固有な地域原則と時代原則が内在し、混在する。数学、物理学、化学にはない鉱物学の学問的魅力は、根本原理と、この固有な地域原理と時代原理の追究にある。日本の鉱物学も、当然、根本原理を追求する学問と「島弧」に位置する日本固有の科学的責任、即ち「島弧鉱物学」の両立が、世界から注視される要求であろう。従って、筑波大学の鉱物学分野も、これらの学問的責任を果たすべく、学生と教師がその責任を共有し、「学生は教師の鏡である」をモットーに、教育と研究に研鑽を積むことを旗印に掲げる。
(2006年4月)