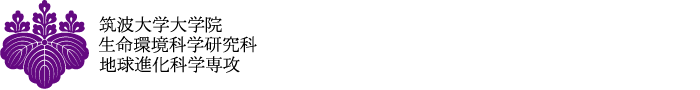■ 鉱物の物理化学特性を電子の挙動から解明する
地球上の鉱物は無作為に生成され、産出しているわけではありません。それぞれの鉱物は、ある特定の温度・圧力・pHといった物理的及び化学的条件下で生成された後、地震や噴火といった過酷な地質イベントを乗り越えて、初めて地表に出現します。鉱物の生成条件や物理的化学的安定性には、その結晶構造や化学結合が大きく影響しています。その結晶構造や化学結合を究極的に決定しているのが、電子の振る舞いです。代表的なものに、Cu2+イオンやCr2+イオンが発揮するヤーン・テラー効果や、Tl+イオン、Pb2+イオンが発揮する不活性電子対効果があります。これらの効果によって、原子の周囲の配位環境が歪んだり、原子間の結合距離が伸びたりすることは古くから知られていました。しかし、このミクロな現象が、地表での鉱物の産出というマクロな現象に及ぼす影響を解明しようとする試みは、国際的にも非常にユニークで、独創的な試みであると言えます。
■ 鉱物の化学組成をより正確に決定する
鉱物の分析方法は、手作業のものから加速器という大型施設を使うものまで実に多種多様です。その中で、最も広く使用されている分析方法が、電子線マイクロプローブ分析(略してEPMA)です。しかし、EPMAの測定は、希土類元素やニオブ・タンタルといった重元素と、炭素、酸素、窒素といった軽元素のが共存する鉱物の場合には、正確な化学組成の決定が非常に困難です。本学の鉱物学分野では、鉱物の化学組成をより正確に決定するために、特に重元素に対する新しいEPMAの分析技術の開発を行っています。
水素の正確な分析は、地球内部での水の挙動や、地表での水−鉱物相互作用などを知る上で大変重要です。しかし、元素の中で最も質量が軽い水素原子は、最も検出が困難な元素でもあります。そこで当分野では、筑波大学研究基盤総合センターにある10階建てのビル程の大きさを持つタンデム型加速器(→)を使用し、鉱物中の水素の正確な分析方法を開発しています。このような大きな加速器が大学内にあり、しかも、それが実験室から歩いてすぐの距離にあるというこは、筑波大学の大きな特徴の一つです。
● 以上のように、筑波大学の鉱物学分野では、正確かつ精密な分析方法を開発し、鉱物が持つ諸現象について結晶構造、組織解析の観点から詳しく解明することを目標にしています。