
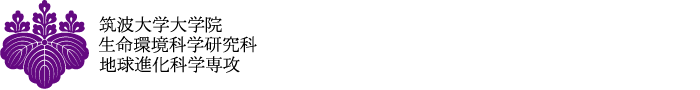
筑波大学鉱物学分野のホームページにご来訪いただきましてありがとうございます。
「鉱物は自然の芸術作品」とは先蹤(せんしょう)の表現であるが、水晶、エメラルド、電気石、ザクロ石などの美晶に魅せられたら、凛(りん)とした万古の緊張感に陶酔してしまう。これは「鉱物の醍醐味」の一面にすぎない。鉱物は、日常生活の到る所で利用されており、この世に生を受けて以来、我々は動物や植物が眼前にない場面に遭遇することはあっても、「鉱物の無い世界」に居たことは無い。ただ身の回りでの鉱物の普遍的な存在を看過しているに過ぎない。従って、鉱物に対する正しい知識を持つことで、より健全な生活、社会を営むことができることは、縄文人による高度なヒスイの穿孔技術、石薬[生薬](例えば、ペリクレース,
MgO,
は通じ薬)、最近のアスベスト(繊維状の蛇紋石と角閃石を含む俗称)公害でも明らかのように、歴史が証明している。
人間には十世(じっせ)があるように、鉱物にも十世がある。十世とは仏教用語で、過去·現在·未来の三世にそれぞれ過去·現在·未来があるから九世(くせ)になり、現在それらが総括されていて、現在を併せて十世になる。地球の十世における過去の三世を考えると、原始地球が層構造に分化するまでの歴史は、岩石の生成がグロ-バルテクトニクスを現出させた。それは先カンブリア代に産出した岩石が種類は少ないものの、一種類の岩石が膨大な産状域を示すことで立証されている。しかし、カンブリア紀以後は、プレートテクトニクスが地球の脈動の主役となり、ローカルな規模で小構造が出現し、連動して多種多様な岩石を産出するに至った。地球を構成する最小基本単位は鉱物であるから、このように地球が物質科学的に変遷していく過程で、いつの世も、鉱物は元素の凝集体として先導的な役割と決定的な存在量で貢献したことは言を俟たない。
では、鉱物とは何か?国際鉱物学連合(1995)では、鉱物の定義を、「鉱物は標準的には、結晶質であり、地質学的な過程を経て形成された、元素または化合物である。」と提唱した。しかし、固体物質としては、通常、結晶、準結晶、非晶質の分類以外に、構成元素の種類によって無機化合物と有機化合物に大別される。自然では4000種類に達する鉱物の殆どが無機鉱物で、有機鉱物は約40種類に過ぎない。いずれにしても、鉱物にはその構成元素の種類と量、さらにその構成元素の周期的配列など様々な情報が内在しており、その科学的意義を解明することが「鉱物学」である。地球の進化と共に変遷した鉱物は「鉱物の生成」「鉱物の結晶構造の構成」「鉱物の物性発現機構」の各原理を覚他し、その十世を通して我々に「科学」を教授する。その意味で、鉱物学は蘊奥を究めるのに値する学問といえる。
(2006年4月)
_____
_____筑波大学大学院生命環境科学研究科
_____地球進化科学専攻 教授 木股 三善